為替手形それでは例題をもとに為替手形の仕訳を学習してみましょう。
前ページで説明したように、為替手形の問題は手形を振出したときと、 決済をした時で仕訳が全部で6通りあります。 6通りすべてまとめてしようとせず、はじめに話した図をイメージして、 振出人・指図人・名宛人と、別々の立場に分けて考えるとかんたんに理解ができます。 まず問題文から誰が何をしたかを確認しましょう。 振出人は九州商店で、 指図人は四国商店で、 名宛人は名古屋商店ということになります。 振出人・指図人・名宛人がだれなのかがわかれば、誰が手形を振出して、だれが代金を支払うのか、 またもらうのかがわかります。 まずは振出人・九州商店の仕訳から。 為替手形を振出した時振出人・九州商店の簿記処理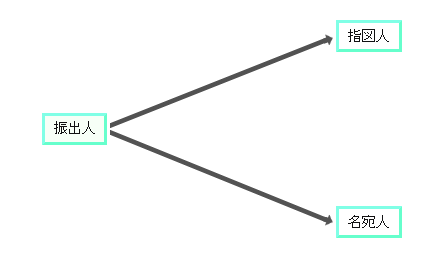
為替手形を振出したときの振出人の場合、どのように処理をしたらいいのかというと、問題文より、振出人・九州商店は名宛人・名古屋商店から引き受けを経て、為替手形を振り出したということですから、振出人・九州商店は名宛人・名古屋商店から受け取る予定の債権、売掛代金分100,000円をチャラ・免除してあげる(売掛金減少)と同時に、名宛人・名古屋商店は振出人・九州商店へ支払う予定だった債務分を指図人・四国商店へ支払うということになります。 また、振出人・九州商店は掛で仕入れた商品100,000円分は、名宛人・名古屋商店から支払ってもらうということになるので、振出人・九州商店は指図人・四国商店に対しての買掛債権は支払う必要がなくなり(買掛金減少)、消滅するということになります。 結果、振出人・九州商店は名宛人・名古屋商店の債権分、売掛金を減少させると同時に、指図人・四国商店への債務分、買掛金を減少させればいいわけですね。
債権と債務の相殺を同時にしています。 また振出人と呼び名がついていて、為替手形を振出していますが、 帳簿上、実際には支払手形勘定科目を使用していないことに注意です。 なぜ使わないかというと、これは手形債権債務を負っていないからです。 指図人・四国商店の簿記処理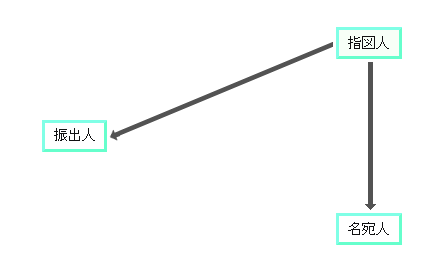
一方の指図人・四国商店でどんなことが起きたかというと 、商品を売却した代金をもとはというと、振出人・九州商店から売掛金として受け取るはずでしたが、 そのかわりに、九州商店から名宛人名義の手形を受け取ったということで、 債権を振替えるという処理をすることになります。 具体的には、振出人・九州商店への債権・売掛金を相殺してあげて、 そのかわりに名宛人・名古屋商店が支払ってくれる、 約束手形を振出人・九州商店から新たに受け取るので、受取手形の増加をさせる仕訳をします。
どちらにしてももらうものはもらう、ということになります。 その債権が売掛金なのか手形なのかという違いだけです。 名宛人・名古屋商店の簿記処理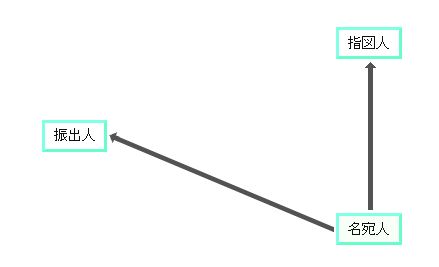
名宛人・名古屋商店は、一言でいうと支払い先が変わったということになります。 名宛人・名古屋商店は振出人・九州商店に対して買掛金が残っていて、 その買掛金の代金を九州商店へ支払うことになるはずでしたが、九州商店へは支払わなくてはいいから この債権の分は四国商店に支払ってください、という呈示を引き受けたので、 名宛人・名古屋商店は振出人・九州商店への買掛金を減少させると同時に、 かわりに振出人・九州商店が振出した手形債権分を増加させるという処理をします。
名宛人も支払うことには変わりはない、ということになります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
【 簿 記 い い な . n e t 〜簿 記 検 定 の 入 門 サ イ ト〜 】Copy right (C) Since 2009/2/25 当サイトの内容・構成・デザイン・画像の無断転載、複製(コピー)は一切禁止です。
