割引手形手形の割引例題をといてみましょう。
問題を解く前に、まずは手形の割引料の計算をします。 割引料の計算(年間トータルを求める)割引料といっても要は利息ですから、一年間にどれだけの利息があったかを求めればいいわけです。 簿記では「何々率の計算」といえば、だいたい一年間のあいだに、 どれだけ何々がかかると、最初に計算で求めることが鉄則です。これは企業の会計期間が一年単位の計算だから、ということが大きくかかわっているんですが、 簿記の問題ではだいたい年何%で出題されるんです。月何%でとは、あまり問題で問わないんですね。 とにかく、先にまず一年間でのトータルの金額を求めます。 手形の額面金額は200,000円です。そして定石どおり、200,000円を一年間割り引いた時の割引料を、まず先に求めます。 実際の金額は、200,000×0.04=8,000で、この8,000円が、割引を一年のあいだにもししていたら、 借り続けていたら8000円がかかりますよ、という金額になります。年間の金額をもとめるのがポイントです。 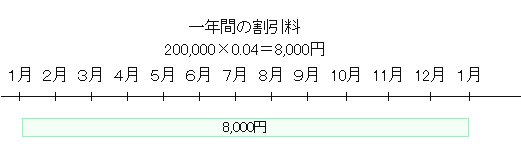 割引料の計算(割引日数を求める)次に、割り引かれた期間の計算をします。一年間で、どれだけの日数、手形が割り引かれていたかが、わかればいいんですね。 問題文より、7月8日から手形の満期日11月30日までの日数をかぞえます。 割引日数は、
割引日数 146日を 365日で割ると、146日/365日=0.4で、一年間のうちの、4割にあたる期間、手形を割り引いていたということになります。 一年間で8,000円でしたから、その4割、0.4年間で、8,000×0.4=3,200円となり、これが問題で求める割引料になります。 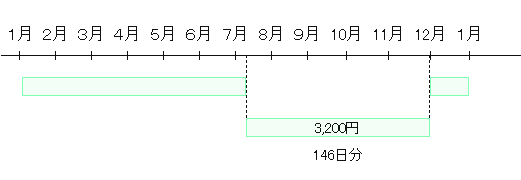 というようにこんな感じなのですがどうでしょうか?
そして仕訳は利息分を手形売却損(または支払割引料)勘定科目(費用)として別勘定を用い、
と仕訳をします。結果、3,200円が費用として消え、 実際に残った196,800円が、この会社で現金としてお金が残ったということになります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 簿 記 い い な . n e t ~簿 記 検 定 の 入 門 サ イ ト~ 】Copy right (C) Since 2009/2/25 当サイトの内容・構成・デザイン・画像の無断転載、複製(コピー)は一切禁止です。
URL ** http://boki.iinaa.net/ ** MAIL ** bokishiken[at]yahoo.co.jp ** [at]は@に置き換えてください 最終更新日07/04/2025 03:51:35
