為替手形為替手形は、手形の振出人が直接支払うのではなく、 売掛債権をもつ取引先、得意先に、売掛金残高から支払ってもらうことを委託した証券です。約束手形は債権者、債務者の2者間の取引で使用されるものでしたが、 為替手形は3者間の取引関係で使われます。 為替手形とは為替手形は、商品売買取引に用いることでは、約束手形と変わらないのですが、 約束手形とは違って、為替手形を振出すための前提条件があります。この条件が整わないと、為替手形を使っても意味がないんです。 為替手形の前提条件
その条件は一体どんな時なのかというと、
A商店にB商店の債務があり、また A商店にC商店の債権がある場合です。 これが為替手形を使う際の前提条件になります。 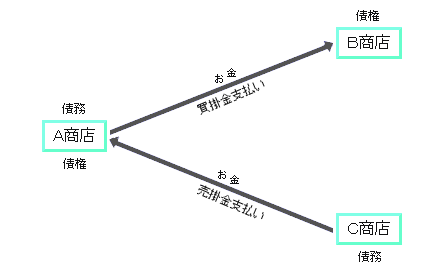
A商店はB商店に債務があるとします。今回、話をわかりやすくするために、 商品を仕入れた代金を債務とした、買掛金とします。 また一方、A商店はC商店に債権があるとします。こちらも話をわかりやすくするため、 商品を販売した未回収の販売代金、売掛金とします。 と、ここまでが前提条件です。 会社の経営していれば、これはよく起こるできごとですね。 仕入先に対しては買掛金が、得意先には売掛金が、取引の性質上自然とよくたまってしまいます。 A商店の店主の思いつき
普段は、C商店からお金を回収して、そのお金をそのままB商店の支払いにあてていた、
A商店でしたが、ここでA商店の店主はふと、こう考えます。
「C商店から売掛金を回収したとしても、 結局B商店の支払いにすぐ出ていってしまう。 支払うの面倒くさいから、何だかムシのいい話だと思うけど、 C商店が自分の代わりに支払ってくれないかな・・・・」 と、思いついたんです。 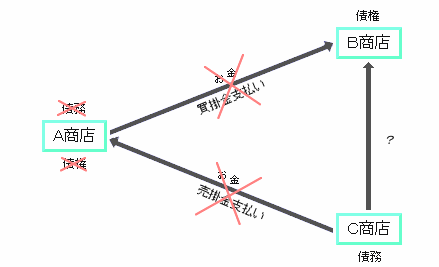
つまりA商店の店主は、「 こっちの支払いチャラにするから、その分向こうへ、オレの代わりに払っておいてよ 」 と思いついたんですね。 この取引を成立させるために、為替手形を使用します。 為替手形の場合、振出人は代金の支払いを委託した人になり、実際に代金を支払う人ではありません。 「 振出人にかわって支払う 」 というのが約束手形と違うところです。 また、A商店・B商店・C商店それぞれ支払う相手、受け取る相手がかわるというだけで、 誰かが損をするとか、得をするとかいうことはないということも為替手形の特徴です。 簿記3級では難解な部分になります。 | |
【 簿 記 い い な . n e t 〜簿 記 検 定 の 入 門 サ イ ト〜 】Copy right (C) Since 2009/2/25 当サイトの内容・構成・デザイン・画像の無断転載、複製(コピー)は一切禁止です。
