為替手形為替手形の話を進めます。突然支払い先を変更されて、そのことをしらないままC商店が2重に支払ってしまってもしかたがないので、 はじめにA商店ではなくB商店のほうへ払ってくれるかどうか承諾をしてもらう話を持ちかけます。 これを引受呈示といいます。 「 これからはあっちに支払って 」 ということになります。 A商店から引受呈示をされたC商店は、 「 いいよ 」 と承認をしてもらい(引受といいます) 引受をしてもらってはじめて、A商店はB商店に為替手形を振出すことになります。 手形を振出したので、この取引は簿記上の取引に該当し、 A・B・C商店それぞれの帳簿上の債権・債務を変更する仕訳処理をすることになります。 その為替手形が無事振出された後は、A商店が抜け、 残ったB商店とC商店の間のやりとりになり、 あとは2者の間ですから、約束手形と同じ決済方法をとることになり、 為替手形に関する一連の経済取引は終わるということになります。 <為替手形処理の流れ>
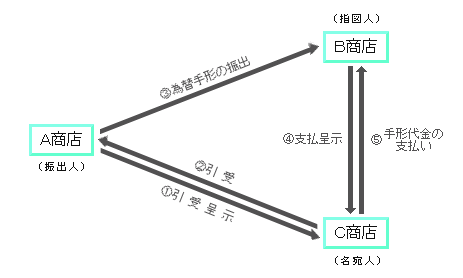 振出人と指図人と名宛人為替手形の流れが大体わかっていただいたと思うので、今度は登場人物についての呼び名の説明です。簿記試験で問題文に「A商店」なんて名前では出ないので(汗)・・・・。 約束手形の登場人物は受け取る人と支払う人、2者の間のやり取りでした。 為替手形の場合は説明の通り3者になります。 為替手形の場合はすこしややこしくなっています。
約束手形では名宛人が債権者になっていましたが、 為替手形では債務者になっています。ここは気をつけて、まちがえないようにしてください。 約束手形の時とは呼び名が違うんだ、ということだけしっていればいいと思います。 また、為替手形の簿記処理をするタイミングとしては、経済活動の記録ですから、 振出人・名宛人・指図人が手形を振出した時の3通りと、 振出人・名宛人・指図人が手形を決済した時の3通りで、合計6通りの仕訳のパターンをそれぞれおぼえることになります。
| |||||||||||
【 簿 記 い い な . n e t 〜簿 記 検 定 の 入 門 サ イ ト〜 】Copy right (C) Since 2009/2/25 当サイトの内容・構成・デザイン・画像の無断転載、複製(コピー)は一切禁止です。
