商品売買では繰越商品勘定はどのような役目になっているのかというと、 仕入勘定の中に入っているまだ売れていない商品分を取り除く、 在庫管理の役割になります。仕入勘定科目は商品として企業に入ってきたすべての「入り」の分しか記録していませんから、 売れた原価分とまだ売れてない原価分の両方が混じって記録されている状態なんです。 ・ 期中の各勘定口座の状態
在庫の分も売上原価にしてしまったら、決算書は信頼のおける報告書ではなくなってしまいますね。 すべての売上金額と、売上の原価分はきちんと対応させなければいけません。 もっと細かくいうと、商品一つに対して利益と原価があっていなければいけませんね。 そういった理由で、売上の原価分を調べることになります。 どうやって原価分と在庫分を見分けるのかかというと、具体的には棚卸し(たなおろし)をします。 決算の時点でお店にある商品を、一つひとつかぞえていくんです。 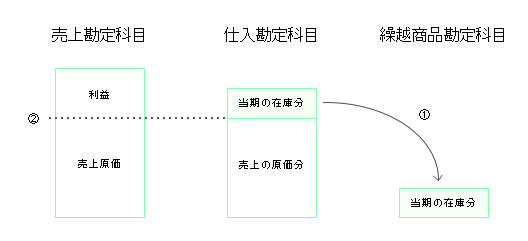
① 棚卸をしたことによって判明した商品の在庫分を、仕入勘定科目から引けば、その残りは
売り上げに対応する正味の売上原価になります。
② 売上勘定科目から、今、在庫分を引かれたことによって正味の売上原価の状態になっている、仕入勘定科目を 差引くことによって、利益が算出されます。 そのため、三分法では決算時に在庫商品の修正、整理が行われ、 売上原価や商品売買益がこれらの3つの勘定口座からまとめられて算出されることになります。 取引が発生したらつぎつぎに仕訳をしていくだけですので、 三分法は商品売買の処理を機械的にしかも大量にできる方法なんですね。 しかし、決算時期は少し手間がかかるというデメリットもあります。 三分法による商品売買益の公式以上のことをまとめると、一つの公式ができあがります。
売値=原価+利益 の方程式の項目を、利益=売値-原価 と変形させて内容を細かくしたものと考えればいいとおもいます。
・商品売買益は利益のことで、純売上高は返品や値引きをしていない純粋な売上金額のことです。
三分法では売上勘定科目を使用して記録します。
その際に、原価+利益は売上勘定科目で、原価は仕入勘定科目を使用して計算することになります。
・売上原価は売上に対しての原価にあたるという意味です。商品仕入高と商品棚卸高で構成されています。 ・当期商品純仕入高は返品・値引きをしていない状態の仕入金額です。仕入勘定科目を使用します。 ・期末商品棚卸高は会計期間期末に棚卸しによって判明した金額です。 ・期首商品棚卸高は前期分の棚卸金額のことで、仕入勘定科目に加算します。 | |||||||||
【 簿 記 い い な . n e t ~簿 記 検 定 の 入 門 サ イ ト~ 】Copy right (C) Since 2009/2/25 当サイトの内容・構成・デザイン・画像の無断転載、複製(コピー)は一切禁止です。
