現金これから簿記の流れの仕訳をするための素となる勘定科目ごとの説明をしていきます。 まずは商売の要、現金から現金勘定1お金の取引が生じた時、現金という資産の勘定科目を用います。現金は文字通り日常使っている紙幣・硬貨のことです。 簿記ではお金はもちろん現金として扱われますが、 簿記上では、他にもいくつか現金として扱うことになっています。 またでてきましたね、一般とは違った、簿記上の概念というやつです。 簿記では、以下のものを現金として扱います。 <簿記上の現金> 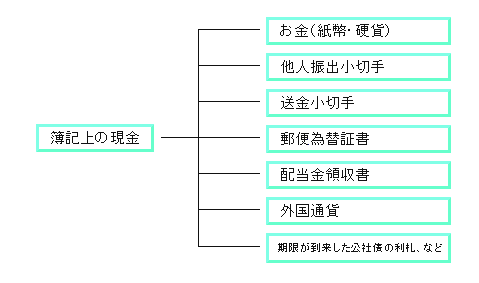
簿記上の現金のなかには私たちが普段使っている、 いちばん上の行のお金(紙幣・硬貨)以外にも、 以下、他人振出小切手、郵便為替証書、外国通貨 ・・・・・・・・、 は、 通貨代用証券(つうかだいようしょうけん)といいます。 通貨のかわりになる証券類という意味でしょうか。 様々な通貨代用証券通貨代用証券について、いくつか説明しておきます。簿記3級の試験では、どんな種類があるか?と、直接に意味を聞かれることはありません。 この章のポイント「通貨代用証券も現金として扱う」ということを知っているだけでいいのですが、 知識として簡単に内容を知っておいてください。 小切手(こぎって)
あまり馴染みがないと思いますが、
企業間での金銭の受け取りや支払いの金額が多額な場合、小切手を使います。
ところで、一億円って重さ約10キロあるの知ってました? 持ち運ぶの結構大変なんですよ。
もし襲われたら確実に逃げきれませんよ。カモネギですよ。危険ですね。
その危険を避けるために小切手という制度が発達したといわれています。
小切手は振出人が、小切手を持参した人に現金へ換金するように銀行に依頼する証書のことです。 「この小切手を持っている人に、書いてある金額を支払ってあげてください」という証券です。 小切手帳なる手帳を、銀行から借りて、使う時は一枚ずつ切り離して 、金額などの必要記入事項を記入して相手に渡します。もちろん銀行口座には、 支払われる額のお金が預けておかなければいけません。 また、小切手を受け取った場合、 もともと現金を持ち歩く危険を避けるためのものですから、 銀行から銀行へと、一度もお金に換金されずに処理される場合があります。 流通性が高いなどと経済学ではいうらしいですが、とにかく簿記上では現金と同様に扱われる、ということです。 また、後ででてきますが、預かった小切手を手もとには置かずに、 すぐ銀行に預け入れた場合、当座預金勘定で処理することになります。 配当金領収書
株をしたことがある方はわかると思いますが、
ある権利確定日までに株券を持っていると、
配当を出す企業であれば、配当金というお金をもらうことができます。
今期は儲かったので、もうかった利益分のいくらかを株主に還元しよう、 という行為です。この行為を、配当といいます。 実際には現金ではなく、振替支払通知書という領収書が郵送されてきて、 それを金融機関にもって行き、現金化するという流れです。 領収書をもっていればいつでもすぐに現金化することができるので、 現金同等物ということで、現金の勘定科目で処理されます。 当然企業も法人ですから、株券を持つことも可能ですし、 株券をもっていれば、配当を受け取る権利も同様に発生します。 配当金領収書も小切手と同じように、換金しないまま、相手に支払うことができます。 期限が到来した公社債の利札
社債は企業の借金です。借金には、利息がつきます。その利息分のことです。これもいつでも
受け取り、支払いが可能なので、簿記上は現金として扱います。
支払がすぐに可能であれば簿記上では現金として扱われることになります。 簿記の世界では現金と通貨代用証券とでは、あまり区別する必要がないんですね。 | |
【 簿 記 い い な . n e t 〜簿 記 検 定 の 入 門 サ イ ト〜 】Copy right (C) Since 2009/2/25 当サイトの内容・構成・デザイン・画像の無断転載、複製(コピー)は一切禁止です。
