貸借対照表は一定時点(決算日)の財産状態を表し、損益計算書は一定期間(一年または6ヶ月)の儲け・損を表しているという話でした。
個々の内容はわかりましたが、今度は貸借対照表と損益計算書には、一体どのような関係があるのかという説明と同時に、財産法と損益法のまとめです。
ちょっとまとめると、財産法は期首資本と期末資本を差引くことによって儲けを計算する方法で、また損益法は一定の会計期間中の収益から費用を差し引くことによって儲けを計算するという方法でした。
| 財産法の計算式から | 期末資本 | − | 期首資本 | = | 純損益 |
| 損益法の計算式から | 総収益 | − | 総費用 | = | 純損益 |
この計算式から財産法と損益法の両者に共通することは、儲け(純損益)が一致するということだということですね。
儲けが増えれば財産が増え、儲けが減れば財産が減ります。
このことから、貸借対照表で計算した当期純利益と、損益計算書で計算をした、当期純利益の金額は、同じ会計期間内であれば、必ず一致するということが導かれます。(貸借一致の原則)
一定期間の計算された利益を通じて、貸借対照表と損益計算書の計算書類はともに結びついているんですね。
また、もし利益が一致しなければ、どこかに間違いがあるという、お互いをチェックしあうことができます。
これが貸借対照表と損益計算書の関係になります。
このことを簿記を離れて経済学ではストック・フローなんてよくいわれますが、簿記や経済学の参考書の例えによく出されるのが、バスタブと水の関係です。
まずバスタブがあって、水が一定の量入っています(資本)。この水をお金と考え、これが元手にあたります。
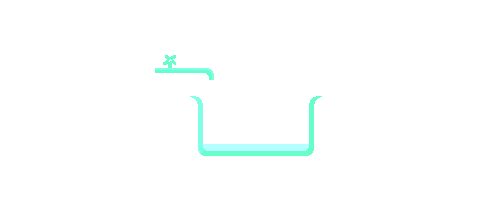
そして第一期、当期中に企業は様々な経済活動を行います。
その間に、水は一定量入ってきて(収益)、またバスタブの栓に穴が開いていたり、蒸発などの理由で水は減ったりもします(費用)
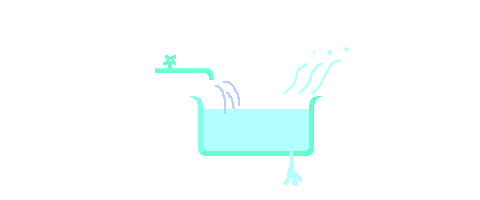
そして決算を迎え、企業はどのくらい儲かったのか、利益の計算をします。
さて、水の量(利益)がどうやってわかるのかということでしたが、二通りありました。財産法と損益法でしたね。
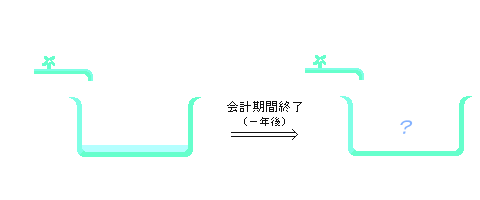
財産法は、期末資本−期首資本=純損益という計算式でした。
財産法にあてはめて、この例の場合を考えてみると、決算日当日のバスタブの水の量から、最初に入っていた水の量を引くことにより、残った水の増減で利益がわかるというのが財産法です。
二つ目の損益法は、バスタブの容器を無視をして、蛇口から出た、水の量と、栓から漏れてしまった水や、蒸発した水の、全ての出入りの量、一切を記録するという方法です。
この方法でも、水の量、利益がわかることになり、簿記の目的が達成されます。
違う方法で計算しているにも関わらず、同じ結果がでてしまうなんて不思議ですね。誰がこんなことを考えついたんでしょうか。
以上、貸借対照表と損益計算書の関係は、利益が一致するということでした。